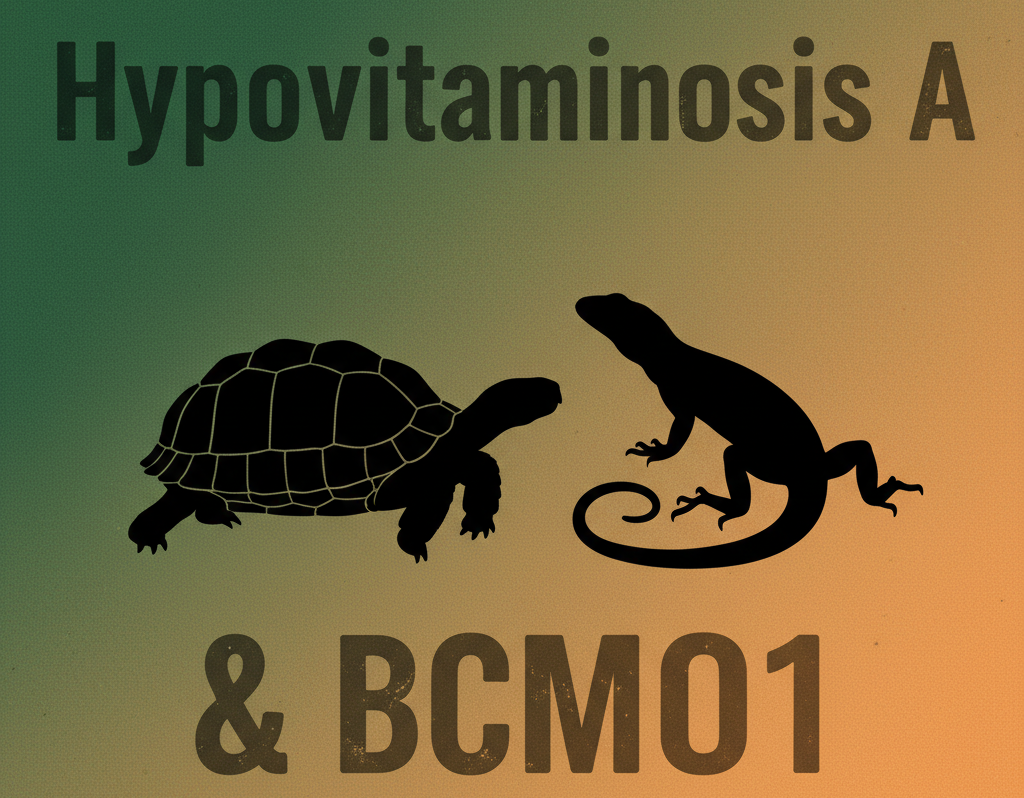背景
βカロチン中央開裂酵素(β-carotene 15,15′-monooxygenase: BCMO1:βカロテン15,15′-モノオキシゲナーゼ)は、植物に含まれるプロビタミンA(カロチンなど)を、動物が利用可能なビタミンA(レチノール)に変換する唯一の酵素です。獣医学において、爬虫類のBCMO1に関する知見は、飼育下の栄養管理と疾病予防に直結する極めて重要です。哺乳類と異なり、爬虫類におけるBCMO1の活性は、種ごとの食性(草食、肉食、雑食)によって著しく異なることが最大のポイントです。
ビタミンA代謝の概要とBCMO酵素の役割
ビタミンA(レチノイド)は、すべての脊椎動物にとって不可欠な脂溶性ビタミンであり、視覚の維持、正常な成長と生殖、免疫機能の調節、そして上皮組織の分化と維持において中心的な役割を果たします。爬虫類の健康管理において、ビタミンAの代謝異常は最も頻繁に遭遇する栄養性疾患の一つであり、その病態生理は種特異的な代謝能力に深く根ざしています。
ビタミンAの供給源
脊椎動物が利用可能なビタミンA源は、化学的に2つの異なる形態に大別されます。
- プレフォームドビタミンA(Preformed Vitamin A):レチノールおよびそのエステル体(パルミチン酸レチニルなど)。これらは生物学的に活性な、あるいはそれに近い形態であり、主に動物の肝臓、卵、乳製品などの動物性食品に含まれます。
- プロビタミンAカロテノイド(Provitamin A Carotenoids):β-カロテン、α-カロテン、β-クリプトキサンチンなど、分子内に少なくとも一つの非置換β-イオノン環を持つカロテノイドになります。これらは植物、藻類、菌類、細菌によって合成され、ニンジン、カボチャ、ケールなどの緑黄色野菜や果物に豊富に含まれます。
これらの供給源のうち、どちらを主要なビタミンA源として利用できるかは、各種動物が持つ酵素、特にカロチン中央開裂酵素(β-carotene 15,15′-monooxygenase: BCMO1)の活性に全面的に依存しています。
BCMO(カロテンオキシゲナーゼ)の分類と基本機能
脊椎動物のゲノムは、カロテノイドの酸化的開裂を触媒する2種類の主要な酵素、すなわちBCMO1とBCO2をコードしています。これら2つの酵素は、その機能、基質特異性、および細胞内局在において根本的に異なります。
BCMO1:ビタミンA生成を担う細胞質酵素
BCMO1(β-carotene 15,15′-monooxygenase)は、プロビタミンAからビタミンA(レチナール)を合成する主要な酵素です。この酵素は、β-カロテン分子の中央二重結合を特異的に認識し、開裂を触媒します。この反応により、1分子のβ-カロテンから2分子のレチナール(ビタミンAアルデヒド)が生成されます。BCMO1は主に小腸の腸上皮細胞や肝臓の細胞質に局在しています。
BCO2:ミトコンドリアにおけるカロテノイド除去
BCO2(β-carotene 9′,10′-dioxygenase$)は、BCMO1とは異なる機能を持つ酵素です。BCO2はカロテノイド分子の非対称的な位置を認識し、開裂を触媒します。この反応で生成されるアポカロテノイドは、レチノイド(ビタミンA)とは異なる代謝経路を辿ります。BCO2の基質特異性はBCMO1よりも広く、プロビタミンA以外の多様なカロテノイド(例:ゼアキサンチン、ルテイン)も切断します。
BCMO1とBCO2の決定的な違いの一つは、その細胞内局在です。BCO2はミトコンドリアに局在し、生理的役割がビタミンA合成ではなく、細胞保護にあることを示唆しています。過剰なカロテノイドがミトコンドリアに蓄積すると、酸化的ストレスを引き起こし、シトクロムcの放出を介してアポトーシス(プログラム細胞死)を誘導することが示されています。BCO2は、これらのカロテノイドを無害なアポカロテノイドに分解することでミトコンドリアを保護する機能していると考えられています。脊椎動物のカロテノイド代謝は、細胞質におけるビタミンA合成(BCMO1)と、ミトコンドリアにおける解毒・除去(BCO2)という、空間的・機能的に分離された二重のシステムによって制御されています〔Lietz et al.2012,Lobo et al.2012〕。
食性によるBCMO1活性の多様性
爬虫類はその多様な進化の過程で、異なる食性適応を遂げてきました。BCMO1の機能は、その食性と強く関連しています〔O’Grady et al.2015,Román‐Palacios et al.2019〕。しかし、爬虫類のゲノム解析は、哺乳類や鳥類と比較して発展途上であり、結果の立証も限定的です。その中でも、スッポンやグリーンイグアナ、ビルマニシキヘビなどの解析では、BCO1およびBCO2遺伝子が爬虫類にも存在し、組織特異的に発現していることが確認されています。現在のところ、臨床的にβ-カロテン変換能力の欠如が示唆されているヒョウモントカゲモドキなどの種において、BCO1遺伝子の機能喪失型変異を分子レベルで特定したという報告は実際には乏しく、これは今後の爬虫類においてる重要な研究課題となっています〔Pinto et al.2023,Zhang et al.2025〕。
草食性爬虫類におけるBCMO1
グリーンイグアナや多くのリクガメ科に代表される草食性爬虫類は、その生涯を通じて植物(葉、花、果実)のみを摂取します。これらの餌はプレフォームドビタミンAを含みませんが、プロビタミンAカロテノイド(β-カロテンなど)を豊富に含みます。これらの種は、摂取したプロビタミンAカロテノイドを、腸管および肝臓においてBCMO1の作用により効率的にビタミンAに変換(合成)する能力を持つと広く結論付けられています〔O’Grady et al.2015,Glaeser et al.2011〕。草食性爬虫類のBCMO1活性は、体内のビタミンA貯蔵レベルに応じて厳密な負のフィードバック調節を受けていると考えられています。体内のビタミンAが過剰している場合、BCMO1遺伝子の発現が抑制され、さらなるビタミンAの合成が停止します。この調節機構が存在するため、草食性爬虫類は、多様な緑黄色野菜を含む適切な食事を与えられていれば、ビタミンA欠乏症を発症することは稀で、同時にビタミンA過剰症のリスクも極めて低いとされています。
肉食性・昆虫食性爬虫類におけるBCMO1
獣医学の臨床現場において、ビタミンA欠乏症は特定の食性を持つ種に集中して発生します。昆虫食性トカゲではヒョウモントカゲモドキ、カメレオン科、アノール属になります。肉食性・雑食性カメでは ヌマガメ科(アカミミガメなど)、ハコガメ属になります。これらの種は、草食性爬虫類とは対照的に、餌のβ-カロテンをビタミンAに変換する能力が著しく低い、あるいは完全に欠如していると考えられています〔Schweizer et al.2020〕。この最も強力な証拠は、臨床現場での観察に基づいています。これらのビタミンA欠乏症が多発する種に対し、β-カロテンのみを含むマルチビタミン剤(ビタミンAの「代用品」として販売されている製品)を投与しても、ビタミンA欠乏症の予防・治療効果が全く見られないという事実です。これは、これらの種においてBCMO1の代謝経路が生理的なビタミンA要求量を満たす上で機能していないことを決定的に示しています。
厳格な肉食動物であるネコにおけるBCMO1の不活性化
肉食性・昆虫食性爬虫類におけるBCMO1機能不全を理解する上で、厳格な肉食動物であるネコは最も優れた比較生理学モデルとなります。ネコが食事中のβ-カロテンをビタミンAに変換することができないのは、BCMO1酵素が機能的に欠損しているためであると結論付けられています 。ネコは進化の過程で、獲物の肝臓や組織に蓄積された豊富なプレフォームドビタミンAを安定的に摂取する食性に特化し、その結果、植物からビタミンAを合成する必要性が失われ、BCMO1の代謝経路が失われた(機能喪失した)と考えられています〔Clugston et al.2014〕。このネコにおける知見は、肉食性・昆虫食性の爬虫類(ヘビ、ヒョウモントカゲモドキ、ミズガメなど)においても同様の進化的適応、すなわちプレフォームドビタミンAへの完全な依存と、それに伴うBCMO1経路の退化・喪失が起こったことを強く示唆しています。
ビタミンA欠乏症
発生機序
本症の発生機序は、BCMO1の機能不全と飼育環境下での不適切な給餌が組み合わさることで成立します。ヒョウモントカゲモドキ、カメレオン、水ガメなどは、BCMO1活性が低いため、β-カロテンをビタミンAに変換できません。これらの種に主食として与えられるコオロギ、ミルワームなどや、一部の安価なカメ用フードは、プレフォームドビタミンAをほとんど含んでいません。コオロギやミルワームに対し、プレフォームドビタミンAを含む高栄養食を与える目的のローディングやダスティングを怠ると、爬虫類は慢性的なプレフォームドビタミンAの欠乏状態に陥ります。
病態
ビタミンAは上皮細胞の正常な分化・維持に必須です。欠乏すると、上皮細胞が角化する扁平上皮化が全身の粘膜で発生します〔Mader 2006〕。これにより正常な分泌・排出機能が失われ、角化物が蓄積し、二次感染を引き起こします。
症状
- 眼症状:ハーダー腺や涙管の扁平上皮化生による閉塞と腫脹(眼瞼腫脹)が特徴的です。眼球内には角化物や粘液の残骸が固形物として蓄積し、眼球を開けられない状態になります。特に水ガメやカメレオンのような視覚に頼る種では、視覚障害が直接的な食欲不振と衰弱につながります。
- 皮膚・口腔・呼吸器症状:皮膚の乾燥、体色のくすみ、脱皮不全、口腔粘膜の扁平上皮化生による口内炎(マウスロット)が特徴的です。呼吸器系の上皮も同様に障害され、鼻炎や肺炎など二次的な細菌性呼吸器感染症を併発しやすくなります。
- その他の症状:トカゲでは、総排泄腔付近のクロアカサックプラグを引き起こすことがあります。重度の場合は腎不全に至ることも報告されています。
ヒョウモントカゲモドキのクロアカサックプラグの詳細な解説はコチラ
治療
治療は、不足しているプレフォームドビタミンA(パルミチン酸レチノールや酢酸レチノール)の投与が必須です。軽症の場合は経口投与や食事改善(ローディングの徹底)が中心となりますが、重症例では注射による投与が行われることもあります。BCMO1の知見が臨床上最も重要となるのは、このローディングの点です。ビタミンA欠乏症を発症した昆虫食性爬虫類に対し、ビタミンA源としてβ-カロテン(プロビタミンA)のみを含むサプリメントを与えても、宿主はそれを活性型のビタミンAに変換するためのBCMO1酵素を持たないため、治療効果は全くないので、注意してください。使用するサプリメントの成分表示を精査し、それがβ-カロテンなのか、あるいはパルミチン酸レチノールなのかを正確に識別し、対象となる種の食性(BCMO1活性)に基づいて適切に選択する必要があります。
| 種類 | 食性 | BCMO1活性 | 必要なビタミンA | ビタミンA欠乏症リスク |
| グリーンイグアナ (Iguana iguana) | 草食性 | 高 | プロビタミンA(植物)で充足可能 | 低(適切な食事の場合) |
| ヒョウモントカゲモドキ (Eublepharis macularius) | 昆虫食性 | 低〜欠如 | プレフォームドビタミンA(動物性)が必須 | 高(プレフォームドA欠如の場合) |
| カメレオン科 (Chamaeleonidae) | 昆虫食性 | 低〜欠如 | プレフォームドビタミンA(動物性)が必須 | 高(プレフォームドA欠如の場合) |
| ヘビ類全般 (Serpentes) | 肉食性 | 低〜欠如 | プレフォームドビタミンA(動物性)が必須 | 低(餌(マウス等)が充足源となるため) |
| リクガメ科(ケヅメリクガメ等) | 草食性 | 高 | プロビタミンA(植物)で充足可能 | 低(適切な食事の場合) |
| ヌマガメ科(アカミミガメ等) | 雑食性〜肉食性 | 低〜欠如 | プレフォームドビタミンA(動物性)が必須 | 高(不適切なペレットや昆虫食の場合) |
| ハコガメ属 (Terrapene) | 雑食性〜昆虫食性 | 低〜欠如 | プレフォームドビタミンA(動物性)が必須 | 高(プレフォームドA欠如の場合) |
ビタミンA過剰症
既成ビタミンA(レチノール)は脂溶性で肝臓に蓄積するため、過剰投与は重篤な中毒を引き起こします。飼育者がビタミンA欠乏症を疑い、ビタミンA(レチノール)のサプリメントや注射剤を不適切に(特に高用量で、またはBCMO1が機能しない肉食性種に)使用することで発生します。既成ビタミンAの過剰は皮膚は赤くただれ、広範囲にわたってスライム状に剥がれ落ちることがあり、しばしば致死的です。
発生
爬虫類におけるビタミンA過剰症の最も一般的な原因は医原性、すなわち獣医療行為によるものです。これは、ビタミンA欠乏症を疑った(あるいは予防目的の)場合、特に注射用ビタミンA製剤の投与量を誤り、過剰投与することによって発生します。ビタミンAの安全域(推奨5,000-10,000 IU/kg)に対し、毒性量(50,000-100,000 IU/kg以上)は比較的高く設定されていますが、注射剤では容易にこの致死域に達する可能性があります。食事性の原因としては、肉食性・雑食性爬虫類(カメ類など)に、プレフォームドビタミンAが極めて高濃度に蓄積されている肝臓(特に肉食獣の肝臓)を過剰に与え続けることで発生する可能性があります。この臨床的現実は、BCMO1の機能に関する知識不足が、いかに深刻な医原性疾患の連鎖を引き起こしうるかを示しています。なお、BCMO1活性を持つ草食性爬虫類においては、このリスクプロファイルが異なります。前述の通り、これらの種ではBCMO1酵素の発現とカロテノイドの吸収が、体内のビタミンAレベルによって厳密に負のフィードバック調節を受けています。ビタミンAが過剰になるとBCMO1遺伝子の発現を抑制し、ビタミンAの過剰な合成を防ぎます 。このため、草食性爬虫類が植物ベースの食事からビタミンA過剰症を発症する可能性は極めて低いとされています。
症状
ビタミンAは脂溶性であり、肝臓にレチニルエステルとして蓄積されるため、体外への排出が遅く、過剰症を引き起こしやすい特性を持ちます。過剰なビタミンAは肝臓の貯蔵能力を超えると、組織障害を引き起こします。初期症状としては、細胞膜を不安定にし、皮膚の乾燥や鱗屑、進行すると、皮膚の広範な水疱形成、表皮剥離および重度の皮膚炎を引き起こします。
まとめ
爬虫類におけるBCMO1の知見は、種によって必要なビタミンAの形態が異なることを示しています。草食性・雑食性種はβカロチンからビタミンAを合成できます。安全性が高いβカロチン(緑黄色野菜など)で供給するのが理想です。ビタミンA欠乏症が疑われる場合は、獣医師の管理下で既成ビタミンA(レチノール)の投与も行いますが、過剰症に厳重に注意する必要があります。肉食性種はβカロチンを利用できません。獲物(マウス、ラット、魚など)を丸ごと(特に肝臓を含む)与えることで、既成ビタミンAを摂取させる必要があります。昆虫食の種(ヒョウモントカゲモドキなど)も、昆虫自体はビタミンA源として乏しいため、ダスト法やガットローディングでビタミンA(多くは既成ビタミンA)を添加したサプリメントが必要です〔Stahl 2019〕。
待望の新刊! 爬虫類の病気百科
ポチップ
エキゾチックアニマル臨床の第一人者 霍野晋吉が贈る、獣医師そして飼育者、ブリーダーまで、全爬虫類関係者へ送る医学バイブル
参考文献
- Antwis RE,Browne RK.Vitamin A in amphibian nutrition and reproduction.Journal of Applied Animal Welfare Science12(4):285-297.2009
- Clugston RD et al.Vitamin A (Retinoid) Metabolism and Actions: What We Know and What We Need to Know About Amphibians.Zoo Biol24.33(6):527-535.2014
- Donoghue S.Nutrition.In Reptile Medicine and Surgery 2nd ed.Mader DR ed.Saunders Elsevier:p251-298.2006
- Divers SJ,Stahl SJ eds.Mader’s Reptile and Amphibian Medicine and Surgery 3rd ed.Elsevier. 2019
- Lietz G et al.Importance of β,β-carotene 15,15′-monooxygenase 1 (BCMO1) and β,β-carotene 9′,10′-dioxygenase 2 (BCDO2) in nutrition and health.ReviewMol Nutr Food Res56(2):241-50.2012
- Lietz G et al.Molecular and dietary regulation of beta,beta-carotene 15,15′-monooxygenase 1 (BCMO1)ReviewArch Biochem Biophys502(1):8-16.2010
- Lobo GP et al.BCDO2 acts as a carotenoid scavenger and gatekeeper for the mitochondrial apoptotic pathway.Development139(16):2966-2977.2012
- Mader DR ed.Reptile Medicine and Surgery 2nd ed.Saunders Elsevier.2006
- O’Grady SP et al.Correlating diet and digestive tract specialization: Examples from the lizard family Liolaemidae.Zoology108(3):201-210.2015
- Oonincx DG,van den Borne JJ,van der Meer IM et al.Digestibility of black soldier fly larvae (Hermetia illucens) fed to leopard geckos (Eublepharis macularius).PLOS One15(5).e0232496.2020
- Pinto BJ et al.The revised reference genome of the leopard gecko (Eublepharis macularius) provides insight into the considerations of genome phasing and assembly.bioRxiv20.523807.2023
- Román‐Palacios C et al.Evolution of diet across the animal tree of life.Evol Lett3(4):339-347.2019
- Zhang J et al.Disentangling the molecular mechanisms underlying yellow body coloration in a soft-shelled turtle.Zool Res46(2):379-387.2025