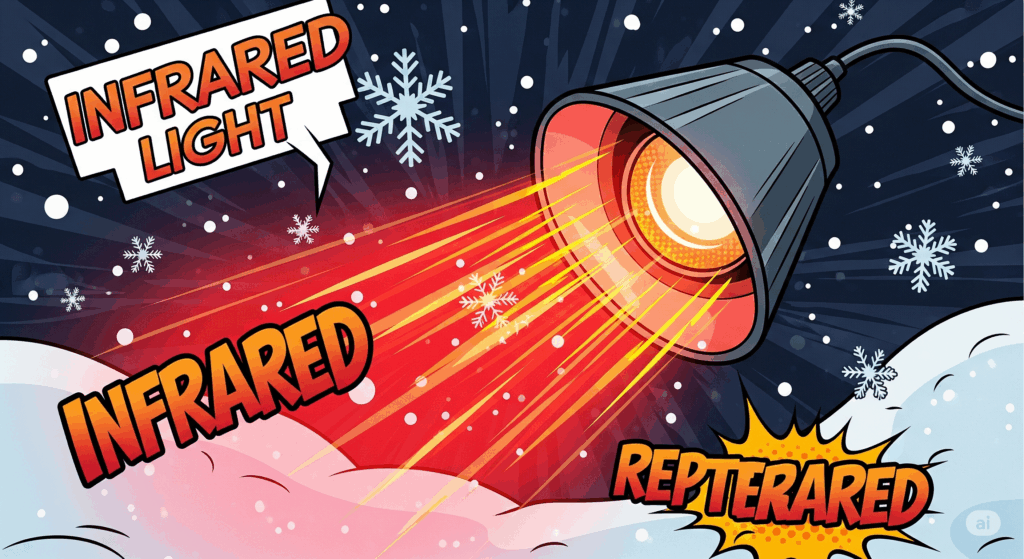保温と光のためのライト
外気温動物の爬虫類にとって、体温を温める日光浴は必要不可欠なものです。しかし、室内での飼育では太陽光が届かないので、保温用のライト(バスキングライト/赤外線ライト)や紫外のためのライト(爬虫類用紫外線ライト)が必要になります。ただし、ライトによる照射も極端に強いと悪影響を及ぼしますので、設置する距離を調節したり、サーモスタットやタイマーと連動させて照射時間を調整します。温帯に生息する種類では、日照時間によって季節を感じ、繁殖の引き金にも重要で、その季節ごとの日照時間にあわせる必要があります。

赤外線ライト = 保温ライト
昼行性の爬虫類は太陽光を浴びて体の調整が行われます。特に至適環境温度域を作る保温効果と骨・甲羅の硬質化という重要な役割を太陽光は担います。変温動物である爬虫類たちは、外からの温度によって体温を維持しています。赤外線を出すライトはバスキングライトとも呼ばれ、人工照明では主に白熱電球に多く含まれているために使用されています。夏はともかく、気温の下がる冬には保温用の赤外線ライトを使ってケージ内を暖めなければいけません。バスキング (Basking) とは、英語で日光浴や日向ぼっこという意味で、一般的に赤外線ライトは、ケージ内の一部にホットスポット (Hot spot) と呼ばれるエリアを作り、爬虫類自身が自由に日光浴や甲羅干しを行える環境を再現するのに使われます。爬虫類は変温動物なので、自ら発熱して体温を調整することができませんので、一時的に体温は上昇して活発に活動し、消化を促進させます。十分暖まると木陰に移動したり、水に入ったりして体温を調整します。

飼育個体へ照射される照明ライトによって作り出される勾配や光源の適合性は、すなわち光の質(スペクトル)と量(動物が受ける放射照度)によって決まります。理想的なスペクトル分布の雛形は太陽スペクトルであり、生命は太陽スペクトルの下で進化し、地球上のすべての生命はこれに適応しています。したがって、ランプのスペクトルと太陽スペクトルを直接比較する必要があります。そして、ライトから任意の距離における放射照度は、つまりランプの出力と光の分布、つまりビームの形状に依存します。
爬虫類・両生類の至適環境温度域 (POTZ)とお薦め温度計/サーモスタットはコチラ

白熱電球
白熱電球とは、ガラス管球の中に入れた高抵抗線に電流を流し、放熱する光を利用するものです。白熱灯から放たれる光のスペクトルは赤外線が多く、熱に変換されます。白熱電球はスペクトルが赤外線の方に偏ったランプなために、可視光も赤~黄色の光が中心となります。なお、ハロゲンランププは白熱電球と同じように、フィラメントに電気を流すことで発光し、電球の内部にハロゲンという物質を加えてフィラメントがより高温にし、一般的な白熱電球よりも明るい光を放射することができます。また、ランプの寿命も白熱電球に比べると長くなる効果があります。
選び方
ワット数
30~100W程度の白熱電球が市販されていますが、ワット数が多い方が優れているわけではなく、ケージや設置環境、動物の種類などによって調整する必要があります。ワット数の目安は幅45cmのケージには30〜50W、幅60cmのケージで50~75W、90cm以上のケージで75~100W内なりますが、設置位置などにより変わってきます。白熱電球以外にヒーターなどで温度を管理されている場合は、ケージ全体が高温になってしまわないようにサーモスタットなどで調整し、朝に点灯し、夕方には消灯できるタイマー付きの商品を使うと管理が楽になります。
高性能
白熱電球はガラス製なので、ぶつけたりすると割れてしまいます。また、水がかかっても割れることがあるため、注意して扱って下さい。水ガメや多湿な環境で飼育する爬虫類では防滴のライトを使うとよいでしょう。白熱電球の寿命も比較的短く、1年前後でフィラメントが切れて使えなくなりますので、常時予備の電球を用意しておきます。なお、外国製よりも信頼がおける国産の商品の方が、フィラメントが切れにいともいわれています。

水ガメの防滴ライト
EXO TERRA¥2,082 (2026/01/28 00:44時点 | Amazon調べ)ポチップ
ポチップ
水ガメライト一人勝ち商品!水がかかってライトが割れてしまうと泣きますよね?水がかかっても割れない強化ガラス仕様の集光型ライトで、湿度を高めに保ちたい種類にもピッタリです。
光の色
白熱電球は赤外線が多いとオレンジ色~赤色を帯びて、保温力が高まります。なお、赤色系の光は爬虫類が見ることができないわれています。

オレンジ色~赤色のランプの明かりは、自然光とはかけ離れているので、爬虫類はホルモンの分泌や精神的にも不調を起こす可能性が示唆されています。対策として太陽光の色温度に近いライトを選ぶか、自然光ライトを併用して使います。
形状
バスキングライトはただの電球にしか見えませんが、散光型と集光型の2つのタイプがあります。
散光型
全方向に可視光と赤外線を放射する散光型はクリア球とも呼ばれ、ケージ全体をじっくりと温めるのに向いています。

集光型
ホットスポットを設けるために、電球内部の首元にアルミを取り付けて、四方八方に散らばってしまう光を1つの方向に反射させるレフ球と呼ばれるタイプの集光型が主流になっています。爬虫類用のレフ球はより反射ビーム範囲を狭く設けることができるため、一部のホットスポットの温度を上げるのに適しています。レフランプのレフは、レフレクター (リフレクター: Reflector) の略で、反射鏡 (reflector) + ランプ (lamp) の造語です。

絶対お薦め集光型のバスキングライト
EXO TERRA¥991 (2026/01/28 00:44時点 | Amazon調べ)ポチップ
EXO TERRA¥1,118 (2026/01/28 00:44時点 | Amazon調べ)ポチップ
EXO TERRA¥1,308 (2026/01/28 00:44時点 | Amazon調べ)ポチップ
バスキングライトで悩んでいるならコレ!同メーカーでホットスポットを作りやすいタイトビームは、同じW数でも他のライトより暖かく、結果的に省エネで、大ヒットしている商品でした。しかし、光がやや赤色を帯びて太陽光とはかけ離れていました。この欠点を改良し、太陽光に近い明りを再現したのが、サングローバスキングスポットランプなんです。
夜用ランプ
夜間の使用に対応した白熱電球として、赤系の光を出すものや、青系の光を出す商品があります。赤系の光を出すライトは、赤色光を認識する錐体細胞が欠けている種類(一部のヤモリなど)が、赤色の光を見づらい点を利用したものです。しかしこれらの種においても、緑錐体が反応するため全く見えないというわけではなく、薄暗い光は感じ取っていると考えられています。
一方で青系の光を出すライトは、夜の月明かり程度の光を再現することを目指してます。保温ライトのため、昼行性の種類でも、冬などの寒い時は24時間点灯させてもかまわないとされています。また、夜間に生体を観察するのに適しています。

しかし、これらの光は爬虫類にとって完全に見えないというわけではなく(赤系の光は種類によっては良く見えている可能性もある)、概日リズムの形成に悪影響を与えないことが保証されているわけでもありません。夜間の保温が必要な場合は、赤外線ヒーターの方が薦めらることがあります。
赤色ライト
EXO TERRA¥2,108 (2026/01/28 00:44時点 | Amazon調べ)ポチップ
ポチップ
ポチップ
昼夜兼用集光型スポットランプ!フトアゴヒゲトカゲなどのトカゲ類、リクガメ類に適しており、昼はバスキング、夜は保温球として兼用できます。気温が下がるとエサを食べなくなるような生体に使って下さい。
バスキングライトでホットスポットを設けて、保温を行いますが、至適環境温度域になっているか、温度計で測定して管理しなければなりません。また、温度が上がり過ぎることで熱中症になる恐れもありますので、そのような時にはバスキングライトにサーモスタットを取り付けて、温度管理を行うべきです。
ソケット
バスキングライトに使用される白熱電球は、電球単体で売られていますが、水槽やケージに取り付けて点灯させるには、電球ソケットやスタンドが必要になります。

時に赤外線ライトの過照射により火傷を負う事故もあるので、電球に直接触れられないようにカバーが必要かもしれません。また、生体がコードを引っ掛けたりして落下すると、火災の原因となることがあります。
白熱電球からLEDランプへの切り替え
白熱電球がLEDに切り替えが現在行われています。爬虫類飼育者は必ず読んで下さい。
まとめ
現在の技術では、人工的なライトによって、太陽光に含まれる全てのスペクトルを太陽光と同じ強度で含む光を放つことは不可能です。フルスペクトルライトなどの名称で、太陽光のスペクトルに近い光を出すというライトが販売されていますが、スペクトルの含有率は近くても強度が不足しているのが現実です。可能であれば、屋外飼育で太陽光や甲羅干しを十分に浴びさせて、人工的な照明ライトと日光を併用しましょう。

待望の新刊! 爬虫類の病気百科
ポチップ
エキゾチックアニマル臨床の第一人者 霍野晋吉が贈る、獣医師、そして飼育者、ブリーダーまで、全爬虫類関係へ送る医学バイブル
動物看護師の教科書
ポチップ
爬虫類好きなら持っていないといけない
両生爬虫類医療を勉強しよう
マニアから獣医師まで対応(今後もう聴けない)