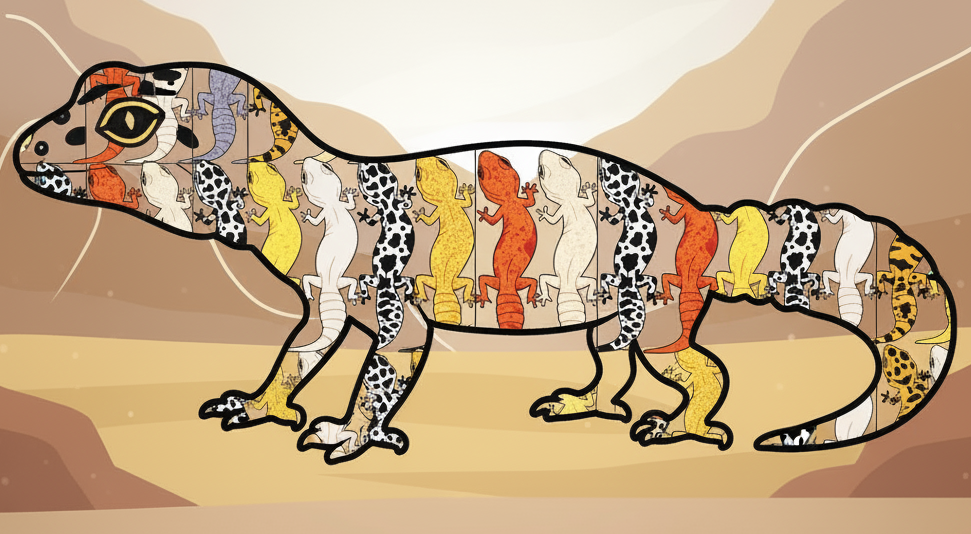雌雄鑑別
身体の大きさと二次性徴で雌雄が鑑別できます。
- 体の大きさ
- 頭の幅
- 前肛孔
- クロアカサック
オスはメスよりも大きく、がっしりとしており、メスと比べて頭部の幅があります。オスは総排泄孔の近位に横一列に並ぶ分泌腺の開口した9~14個の前肛孔(ぜんこうこう)が発達しています。

メスは前肛孔が目立たちません。

オスは尾基部にはヘミペニスが収納されているクロアカサックがあるため、2つの膨らみが確認できます。しかし、この膨らみはあまり目立ちません。総排泄孔(肛門)周囲を押すとヘミペニスが出てくることでオスと判別できます。

繁殖
性成熟
繁殖可能なサイズはオスは50g、メスは45gといわれています。10~24ヵ月齢で、そのぐらいのサイズまで成長します〔Kramer 2002,de Vosjoli 1990,Kramer 2002〕。性成熟を迎えて発情します。オスは精子ができるようになり、メスは卵を産むことができるようになります。
繁殖期
発情期は年に1度の季節繁殖を持ち、おおよそ1~9月です〔Kramer 2002,de Vosjoli 1990,Kramer 2002〕。普段は単独で生活していますが、反初期には緩いコロニーを形成するとも言われています。
なお、オスもメスも特有の発情兆候が見られますので、メスには特に栄養をしっかりと採らせてください。特にカルシウムが欠乏しやすいので、カルシウム剤を含めたミネラル剤やビタミン剤の投与は心がけて下さい。
爬虫類・両生類向けカルシウム剤サプリメントの解説とお薦め商品はコチラ
オスの発情徴候
野生でのコロニーでは、優位なオスは他のオスに対して、身体を硬直させた脚で持ち上げて威嚇したり、後肢を下げて前肛孔の臭腺からのワックス状の分泌物を地面に塗りつけたり、分泌物をなめて体中に塗りつけたり、塗りつけた身体を石やその他の物体にこすりつけて縄張りを主張したりします。突進したり、うなり声を上げたり、シューシュー鳴いたり、体を反らせたり、尾を叩いたりして縄張りを守るような行動を見せます。しかし、単独で飼育している場合は、このような威嚇行動は見られません。発情したオスは精液の乾燥した塊が総排泄孔に付着していたり、発情が強くてヘミペニスが出っぱなしになってペニス脱になることがあります。

【病気】ヒョウモントカゲモドキの直腸脱とペニス脱(お尻から何かでている)の解説はコチラ
メスの発情徴候
成熟したメスは、オスがいなくても無精卵を産みます。卵胞ならびに卵が大きくなり、拒食することも多いです。これが生理的な妊娠なのか、あるいは卵胞や卵が変性して変性卵胞や変性卵による卵塞が起こることもあります。下のX線写真をよく見ると腹部に楕円の構造物があるのが分かりますか?ヒョウモントカゲの卵は生理的に軟卵なので、X線に卵殻が明確にうつらないのが特徴です。環境が卵を産むのに適していないと、卵胞が排卵して卵になる前に吸収するような現象が起こることがあります(卵胞吸収)。これは生理的現象なので病気ではありません。

交配
オスとメスを1頭ずつ同居させます。オスは発情し尾を激しく震わせて雌にアプローチし、首の横をかんでメスに乗ります。メスの尾を持ち上げ、オスはメスの尾の下に尾を絡ませて総排泄孔を近づけて交尾が始まります。メスの体が震えれば挿入が成功したことを示し、この姿勢で5~10分間留まります。オスのアプローチが始まらない場合でも、2~3日一緒にしておいて様子を見て下さい。オスとメスの相性が悪いようであれば、無理に同居させないほうがよい場合もあります。オス1頭に対して複数のメスを同居させてもかまいません。
抱卵
交尾後10~20日位でメスは体の中に卵を持ちます。最初の小さい卵(卵胞)ではほどんど外貌からは分かりませんが、次第に腹部が膨満します。

卵が大きくなると、腹面にうっすらと卵が透けて見えてきます。ヒョウモントカゲモは、一度に産む卵は通常2個なので、2つの白い影が特徴です。

産卵床
メスはケージの中を落ち着かなく動き回ります。地面を掘るような行動をするでしょう。産卵に適した場所を探し、穴を掘りたがっているのです。自然界でも地面に穴を掘り、その中で産卵します。掘る行動が産卵の引き金になっていると思われるので、飼育下でも掘れる場所(産卵床)を提供する必要があります。産卵スペースとして、メスの体が入るくらいの深めのタッパーなどの容器に、軽く湿らせた土を敷いたものを用意します。産卵床に使う床敷は、バーミキュライト、黒土、水ゴケなどが使われます。容器に出入口の穴と通気孔をあけた蓋をし、ヒョウモントカゲが自由に出入りできるようにしてください。容器の内部は保温し、適度な湿度があった方がよいので、産卵床の下にフィルムヒーターなどを敷き、定期的にスプレーなどで水をまきます。

抱卵期間は個体差があり、短いと2週間~長いと2ヵ月近く卵をもったままの状態です。卵を持ったメスは消化管が圧迫されて拒食を示しますが、それは正常な行動です。産卵までの間は、水分だけは頻繁に摂取するので、新鮮な水だけは用意しておいて下さい。ヒョウモントカゲモドキの卵は滑らかでしなやかな羊皮紙のような卵殻で、大きさは 31~35×13~16mmになります。ヒョウモントカゲモドキの性の決定は温度依存性決定と呼ばれ、25.6~27.8℃でメス、29.4~30.6℃でオスが多く産まれます〔Kramer 2002,de Vosjoli 1990,Kramer 2002〕。産卵は2個/回で、最大6回/年産むことができます〔Kramer 2002,de Vosjoli 1990,Kramer 2002〕。

孵化
産卵したヒョウモントカゲモドキをケージに返したら、卵を慎重に掘り返して孵化をさせます。爬虫類の卵は胚が出来るまで(約1日?)は転がっても問題ありませんが、胚が形成された後に転がって上下逆にすると卵が死にます。基本的に卵は見つけた時の向きのまま保管するために、マジックなどで上部に印を付けます。ヒョウモントカゲモドキの卵の孵化には1~2ヵ月位かかります。温度は25~30℃で、湿度は80~90%を保つように環境を設けてください。孵卵用床敷は、バーミキュライト、ミズゴケ、ピートモスなどが使われます。卵は衣装ケースやプラケースなどがよく使われます。最近ではハッチライトという孵化専用の床材も販売されています。乾燥を防ぐために、蓋はしておきますが、蓋の代わりに、ラップなどを使用します。通気性をもたるために、ラップの蓋に針で、いくつか穴を空けておきます。市販の鳥類用の孵化器を使うのもよいですが、転卵(回転する)機能がオフに出来る商品を選んで下さい。
検卵
産卵2~3日で卵の中に血管が発生します。卵は薄い殻に覆われているので暗い場所で下から懐中電灯等で照らせば血管の確認ができて、有精卵と判断できます。卵に光をあてることをキャンドリング(Candling)と言います。無精卵の場合は、産卵1~2週間で潰れてしぼんできます。

amazon.co.jp/ziyue-検卵ライト-孵卵機懐中電灯-ダチョウ-Grey/dp/B0CR3N5G5L/ref=pd_sbs_d_sccl_2_1/355-6931464-8502543?pd_rd_w=ZAzjb&content-id=amzn1.sym.2d5211c1-2026-47b5-a165-5af5d54b0730&pf_rd_p=2d5211c1-2026-47b5-a165-5af5d54b0730&pf_rd_r=RHVMX37B62R7XH4N51QW&pd_rd_wg=CuqoA&pd_rd_r=209630f1-5f37-4d93-9c94-144679230a6c&pd_rd_i=B0CR3N5G5L&th=1
出生
出生直後のヒョウモントカゲモドキにはヨークサック(Yolk sac)とよばれる栄養の袋がお腹にぶら下がっています。動き出した幼体のヨークサックを切らないようにし、新たなゲージを用意して移してあげましょう。ヨークサックからの栄養をとるので、すぐには餌を食べません。ヨークサックから栄養を取り終えたトカゲの幼体は初回の脱皮を数日以内にして、初めて自分で口から餌を食べるようになります。
| 繁殖形式 | 卵生 |
| 性成熟 | 10-24ヵ月 |
| 繁殖期 | 季節繁殖(1-9月) |
| 産卵数 | 2個/回、最大6回/年 |
| 性決定 | 温度依存的性決定(25.6-27.8℃でメス、29.4-30.6℃でオスが多く生まれます) |
待望の新刊! 爬虫類の病気百科
エキゾチックアニマル臨床の第一人者 霍野晋吉が贈る、獣医師、そして飼育者、ブリーダーまで、全爬虫類関係へ送る医学バイブル
参考文献
- Grenard S.An Owner’s Guide to a Happy Healthy Pet:The Bearded Dragon.Howell Book House.New York.1999
- Johnson JD,Bearded Dragons.Exotic DVM8(5).Zoological Education Network:p38-44.2006
- McKeown S.General husbandry and management. In Reptile medicine and surgery. Mader DR ed.WB Saunders. Philadelphia:p9-19.1996
- Quinn AE,Georges A,Sarre SD,Guario F,Ezar T,Graves JA.Temperature sex reversal implies sex gene dosage in a reptile.Science316:411.2007
- Tosney K.1996.”Caring for an Australian Bearded Dragon” (On-line). Accessed November 16.1999 at http://www.ualberta.ca/~rswan/ERAAS/bd.htm.
- Zoffer D,MazorligT.The Guide to Owning a Bearded Dragon.T.F.H.Publications.Neptune City.NJ.1997