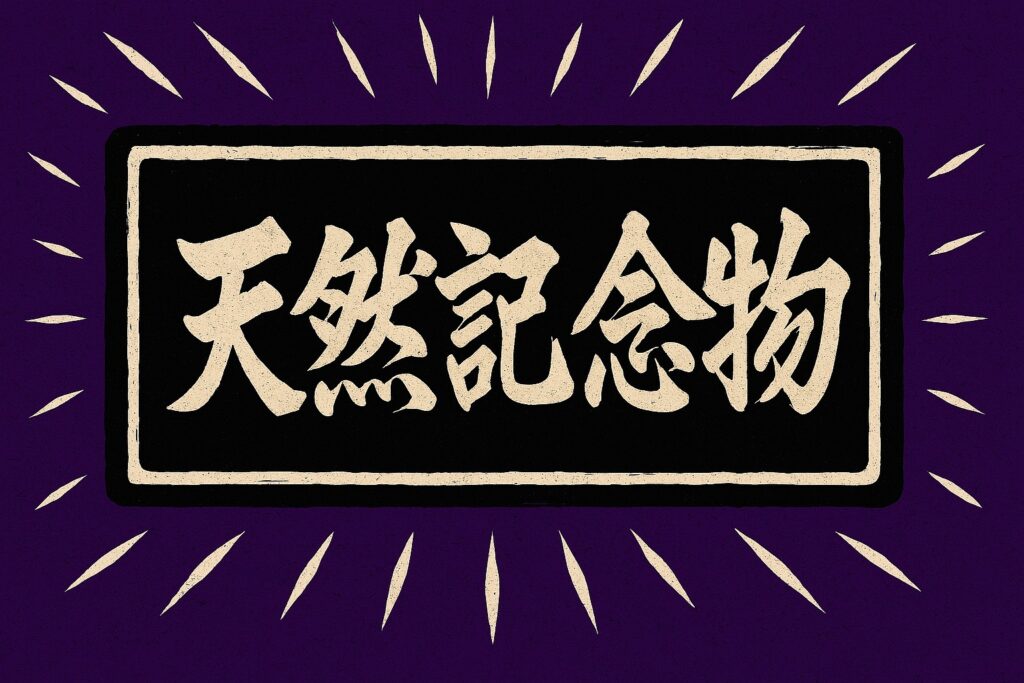天然記念物とは、動物、植物、地質・鉱物などの自然物に関する記念物で、日本においては文化財保護法や各地方自治体の文化財保護条例に基づいて指定されています。生体は許可なく捕獲や飼育は禁止されています。生体の種以外にも、生息地、繁殖地、渡来地などの天然保護区域も指定されています。日本で単に天然記念物と言った場合、国が指定する天然記念物を指します。これらの中には、長い歴史を通じて文化的な活動により作り出された二次的な自然も含まれています。また天然記念物のうち、世界的又は国家的に価値が特に高いものは特別天然記念物に指定されています。
特別天然記念物
オオシサンショウウオ
オオサンショウウオは両生類として唯一、国の特別天然記念物に指定され、日本固有種は日本にしか生息していません。世界最大級の両生類でもあり、全長1.5メートルにもなります。<di約3000万年前から姿を変えていないことから、生きた化石とも呼ばれ、学術的に貴重な生物です。オオサンショウウオは地域を定めない指定であるため、日本国内のどこにいる個体でも保護の対象となります。しかし、近年は、河川改修やダム・堰堤建設による生息地の破壊、近畿地方の一部では人為的に移入されたチュウゴクオオサンショウウオとの競合および交雑により、生息数は減少し、以前は食用とされることもありました。
天然記念物
オオサンショウウオの生息地
オオサンショウウオの分布は岐阜県以西の本州や大分県に分布し、各生息地が天然記念物として指定されています。大分県宇佐市が南限とされています。
- オオサンショウウオ生息地〔岐阜県郡上市和良町・八幡町〕
- オオサンショウウオ生息地〔岐阜県郡上市大和町〕
- オオサンショウウオ生息地〔岡山県真庭市〕
- オオサンショウウオ生息地〔大分県宇佐市〕
カジカガエルの生息地
鳴き声から和歌の題材になったり(夏の季語[注釈)、また美清流の歌姫とも呼ばれとても美しい声で鳴くことが特徴です。
- 湯原カジカガエル生息地〔岡山県真庭市〕
- 南桑カジカガエル生息地〔山口県岩国市〕
モリアオガエルの生息地
モリアオガエルは日本の固有種で、本州と佐渡島に分布しています。水面上にせり出した木の枝や草の上、地上などに粘液を泡立てて作る泡で包まれた卵塊を産みつけることが、特徴的とされています。生息地の森林などの理由により、生息数が減少しています。
- 大揚沼のモリアオガエルおよびその繁殖地〔岩手県八幡平市〕
- 平伏沼モリアオガエかル繁殖地〔福島県双葉郡川内村〕
岩国のシロヘビ
岩国のシロヘビは、山口県岩国市に生息するアオダイショウのアルビノである白蛇で、遺伝によって白化が子孫の代にも受け継がれています。一般には自然下ではアルビノの出現は稀であり、岩国のシロヘビの場合、人間の飼育下ではないにもかかわらず、高い頻度でアルビノが出現していた。これは、地域の人々が昔からシロヘビを神の使いとして特別で大切なものと扱ってきたのが理由であろうといわれています。しかし、近年は生息域内の都市化が進み、米倉、水路、石垣といったシロヘビの棲みかが減少し、天然のシロヘビはその個体数を減らし、岩国市内の6か所にシロヘビの繁殖育成施設等を設けるなどの、保護策を講じています。アオダイショウのアルビノ自体は、岩国市以外の日本各地からも報告されている。
アカウミガメの産卵地
日本では、アカウミガメ(福島県から沖縄県)、アオウミガメ(小笠原諸島や南西諸島)、タイマイ(沖縄県)の3種類のウミガメが日本の砂浜で産卵します。
日本で産卵するウミガメのうち、産卵数が多いのがアカウミガメです。日本は世界でも有数のアカウミガメの産卵地であり、また、北太平洋では、日本列島の砂浜でしか卵を産みません。 最も産卵数が多いのが鹿児島県の屋久島で、千葉県は日本の産卵地の北限なので、南の地方ほど多くはありません。しかし、漁業による混獲、人工構造物による砂浜からの砂の流出による繁殖地の破壊などによる影響が懸念され、ウミガメの産卵地は減少しています。なお、ウミガメは、種の保存法において国際希少野生動植物種に指定されており、生きた個体だけでなく剥製やその一部についても、販売・頒布目的の陳列や、譲渡し等は原則として禁止されています。しかし、ウミガメの保護を全般的に包括する法律は日本にはありませんが、一部の地域では、ウミガメとその卵や産卵地が天然記念物に指定されています。。
御前崎のウミガメおよびその産卵地〔静岡県御前崎市〕
大浜海岸のウミガメおよびその産卵地〔徳島県海部郡美波町〕
キシノウエトカゲ
宮古列島や八重山列島に生息する日本固有種のトカゲで、最大全長は40cmになる日本に分布するトカゲ亜目の構成種では最大種です。人為的に移入されたインドクジャク・ニホンイタチ・ノネコによる捕食などにより生息数は減少しています。
見島のカメ生息地〔山口県萩市〕
日本海に浮かぶ山口県萩市の見島は、約6万~1万年前、地球の寒冷期全体に海面が低下して本州と陸続きでした。その後、地球が暖かくなり、海面が上昇して島となったもので、これらのカメそのものは本州の各地に生息しており、珍しい動物ではありません。地球の寒冷期に本州と陸続きであった時代から生息しているイシガメとクサガメの生息地として、見島小学校の北側にある「片くの池」と呼ばれる約2万㎡の池が指定されています。
セマルハコガメ
セマルハコガメは、中国に生息するチュウゴクセマルハコガメ と石垣島と宮古島に生息するヤエヤマセマルハコガメの亜種に分類されています。 ヤエヤマセマルハコガメは日本固有種で、天然記念物として指定されています。開発による生息地の破壊、道路脇の側溝による生息地の分断および滑落死、交通事故などにより個体数が激減しています。しかし、中国産の基亜種セマルハコガメとの識別は難しく、自然分布域外で見つかる本種がどちらなのか判然としない場合もあり、そのためペット用で密猟もされています。また、在来カメが生息する地域では、交雑による遺伝的撹乱が懸念されます。沖縄島では、セマルハコガメと在来の希少種リュウキュウヤマガメの交雑個体が発見されています。
リュウキュウヤマガメ
日本(沖縄島北部、久米島、渡嘉敷島)固有種のカメで天然記念物に指定されています。開発による生息地の破壊、殺虫剤や除草剤による獲物の減少および本種自体の中毒、道路での車による轢死、道路脇の側溝への落下死などにより生息数は激減しています。頭部の色彩は橙色、暗黄色、黄褐色などで、不規則に赤色や橙黄色の斑紋や筋模様が入ります。人為的に移入された野犬やノネコ、フイリマングースの侵入、ペット用の密猟、クサガメやセマルハコガメ、ミナミイシガメと本種との間にできた属間雑種が発見されており遺伝子汚染などによる生息数の減少も懸念されています。